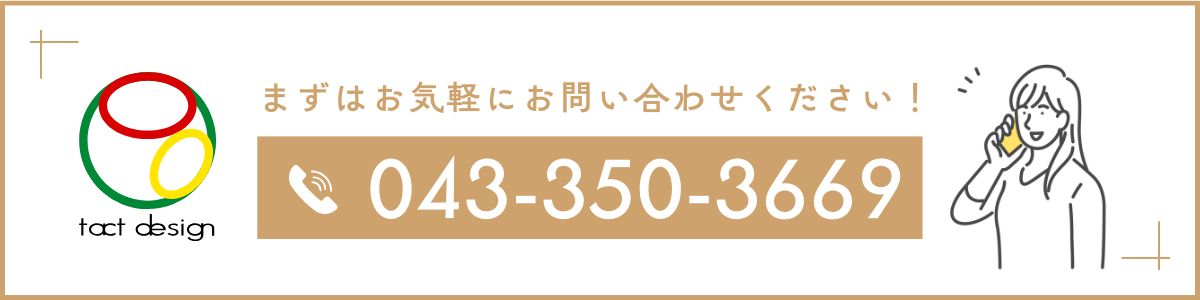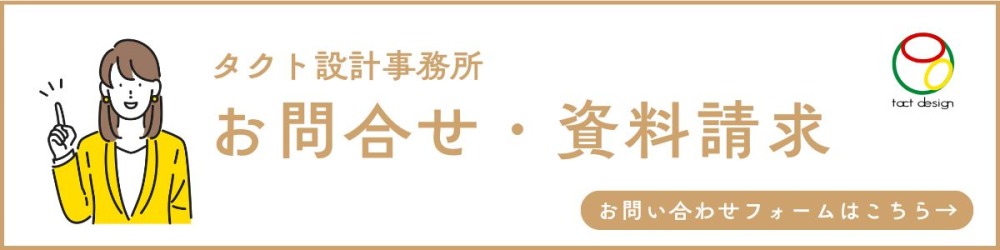「こんなところにコンセントがあればよかったのに…」
家を建てたりリフォームした後に、後悔するポイント第1位に挙がるのがコンセントの位置です。
とくに最近は、スマホやタブレット、ルンバや電気自動車など…
家庭内の電化製品がどんどん増えていて、「どこに・いくつ必要か?」をしっかり考えないと、生活が不便に感じてしまうことも。
-
「新築やリフォーム前に、コンセントの正解が知りたい」
-
「家具を置いたら使えない…失敗しない位置は?」
-
「使いやすい配置って具体的にどこ?」
そんな方に向けて本記事では、
失敗しないコンセントの位置の考え方・部屋別の最適配置・後悔しないためのチェックポイントまで、
まるっと丁寧にわかりやすく解説していきます!

【今回の記事のポイント】
✔︎ コンセントの位置決めは生活動線と家電配置がカギ
✔︎ 部屋ごとの使い勝手に合ったコンセント配置が快適な暮らしを左右する
✔︎ 失敗しやすい場所や後悔しがちな例を事前に知っておくことが重要
目次
- コンセントの位置どこが正解?後悔しない考え方
- 部屋別|失敗しないコンセントの位置と個数
- 家電別に見る「あると便利なコンセント位置」
- コンセント位置を決めるときの5つのチェックリスト
- まとめ|暮らしやすさは“位置”で決まる
コンセントの位置どこが正解?後悔しない考え方
コンセントの位置は、家づくりやリフォームの満足度を大きく左右します。便利さだけでなく、安全性や見た目にも影響する重要なポイントです。しかし、「とりあえず適当に配置してしまった…」「家具を置いたら隠れた!」と後悔する人も少なくありません。まずは正しい考え方を身につけることが、後悔しない第一歩です。

そもそもコンセントの位置をどう決める?
コンセントの位置を決めるときに大切なのは、「生活動線」と「家電の使用場所」を軸に考えることです。たとえば、掃除機のコードが届かない場所や、スマホの充電場所がベッドから遠いと、毎日の生活にストレスが生まれます。
「ここで何をするか?」「何を使うか?」という視点で考えると、自ずと必要な場所が見えてきます。さらに、使用頻度の高い家電(冷蔵庫・テレビ・電子レンジなど)は、設置場所が決まっていることが多いため、その近くに配置するのが基本です。
また、家具との位置関係も要チェック。後からソファや棚で隠れてしまうと、使いたくても使えない状態になってしまいます。

コンセントで後悔した人の共通点とは?
「失敗した…」「もっと考えておけばよかった…」
実際にコンセント配置で後悔している人には、いくつかの共通点があります。
1つ目は、「とりあえず部屋の四隅に設置すればいいだろう」となんとなくの配置にしたパターン。
これでは生活スタイルに合わない場所に設置されてしまい、結局使いづらくなります。
2つ目は、将来の使い道を考えていなかったケース。今は使わなくても、将来的に在宅ワークを始める、子どもが増えるなど、ライフスタイルは変化します。
3つ目は、見た目やインテリアを重視しすぎた配置です。コンセントの存在感を消そうとしすぎると、実用性が犠牲になることもあります。
⬇︎⬇︎お問い合わせはこちらから⬇︎⬇︎
部屋別|失敗しないコンセントの位置と個数
コンセントの位置は部屋ごとに「使い方」や「動線」が異なるため、一律に決めるのはNGです。
リビング・寝室・キッチン・洗面所など、それぞれの用途に合わせた配置が必要不可欠。
ここでは各部屋の使い勝手に合った「ベストなコンセント配置」と「よくある失敗例」を具体的に解説します。
部屋ごとの違いを知ることが、後悔しない家づくりのカギになります。

リビングのベストな配置とよくある失敗例
リビングは家族が集まる場所であり、家電製品も多いため、最もコンセントの設置計画が重要な部屋です。テレビ、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加湿器、スマホの充電…と、想像以上に使うシーンがあります。
おすすめは、テレビ背面の壁に3〜4口。さらに、ソファ近くや壁際に1〜2口があると便利です。スマホやノートパソコンの充電、フロアライトの設置にも対応できます。
ただし、よくある失敗は「家具で隠れて使えない」「掃除機のコードが届かない」「コードだらけで見た目が台無し」など。あらかじめ家具の配置をシミュレーションしてから位置を決めるのがベストです。

寝室のコンセント配置はベッド位置がカギ
寝室のコンセントで最も大切なのは、「ベッドの両サイドにコンセントを設ける」ことです。
スマホの充電、照明、目覚まし、加湿器など、ベッドのそばで使いたい機器は意外と多いもの。
特に、左右どちらにも使えるように配置しておくと、模様替えや将来の使い方にも柔軟に対応できます。
また、床に近い位置よりも、枕元の高さ(60〜90cm程度)に設置すると、抜き差しもしやすく、ホコリや水濡れの心配も減らせます。
寝室は「静かに過ごす場所」なので、延長コードや配線が視界に入らないようにしておくと、落ち着いた空間を保てます。

キッチン・洗面所の位置選びは水回り対策が重要
キッチンや洗面所では、家電の使用頻度が高く、しかも水回りであるため、安全性と使いやすさの両立が必要です。
キッチンでは、電子レンジ・炊飯器・電気ケトル・トースター・食洗機など、それぞれの配置を想定してコンセントを設けます。
特にカウンター下や吊戸棚の中にも設けておくと、コードが見えずスッキリします。
洗面所では、ドライヤー・ヘアアイロン・洗濯機などが主な使用機器。水濡れ対策として防水カバー付きのコンセントを選ぶのが基本です。

子供部屋で配慮すべき位置と安全性のポイント
子供部屋では、「安全性」と「成長に合わせた柔軟性」の2つが重要です。
コンセントは子どもの手が届かない高さ(1m以上)に設置するのが理想で、シャッター付きタイプを選ぶと、感電やいたずら防止にもなります。
また、学習机やベッドの位置を想定し、将来パソコンやゲーム機を使うときのために余裕を持った口数を設けておくのがポイントです。

在宅ワーク部屋は動線と配線を意識
在宅ワーク部屋では、パソコン・モニター・プリンター・スマホ・Wi-Fi機器など複数の電源を同時に使う前提で設計しましょう。
デスクのすぐ下や足元に複数口のコンセントを設置すると便利ですが、配線がごちゃつかないように、ケーブル収納や電源タップ用の棚を確保するのもポイントです。
また、リモート会議の背景にコードが映り込まないよう、美観にも配慮した配置がおすすめです。
⬇︎⬇︎お問い合わせはこちらから⬇︎⬇︎
家電別に見る「あると便利なコンセント位置」
コンセントの配置で後悔しやすいのが、「家電の場所と合っていない問題」です。
特に冷蔵庫やテレビなど大型家電は一度設置すると動かすのが難しいため、
あらかじめ家電ごとに「どこで使うか」「どの向きか」「常時使用か」を考えておくことが大切です。
ここでは、使用頻度が高い代表的な家電に絞って、失敗しない配置ポイントを解説します。

テレビ・レコーダー周辺は裏側+αが必須
テレビ周りには、意外と多くの機器が集中します。
テレビ本体はもちろん、レコーダー、ゲーム機、サウンドバー、Wi-Fiルーター、Fire TV Stickなど…。
これらを接続するには、最低でも4~6口のコンセントが必要になることも珍しくありません。
また、テレビを壁掛けにする場合は、設置高さに合わせてコンセントの位置も調整しておくこと。
コンセントが低すぎるとコードが垂れて見えてしまい、見栄えが悪くなります。
壁掛けでなくても、テレビ台の裏側に設置するのが基本。
ただし、「差し込みにくい」「熱がこもる」などの問題が出やすいため、通気性や作業スペースの確保も意識しておきましょう。

掃除機・充電式家電の使いやすい配置とは?
掃除機、とくにコードレス掃除機やロボット掃除機を使用している家庭では、充電スポットにコンセントが必要になります。
設置の際は、「戻ってきた掃除機が自然に充電できる場所」「邪魔にならずコードも目立たない場所」を選ぶのがベストです。
おすすめは、廊下や収納スペースの中。普段の生活動線を妨げず、見た目にもスッキリします。
また、階段近くに1口あると、上下階の掃除時にも重宝します。
ロボット掃除機を使う場合は、左右1m以上のスペースが必要な機種もあるため、壁際に「専用の帰還スペース」を確保し、その近くにコンセントを配置しましょう。

冷蔵庫・電子レンジ周りは熱と位置に注意
キッチンの中でも、冷蔵庫や電子レンジは設置場所が固定されやすく、熱も発生する家電です。
そのため、コンセントの位置や数をしっかり考えておかないと、見た目だけでなく安全性にも悪影響が出てしまいます。
冷蔵庫は壁ギリギリに置くことが多いため、左右どちらにコンセントがくるかを事前に確認しておく必要があります。
多くの冷蔵庫は背面右上にプラグがあるため、壁の右上(高さ100〜120cm)あたりにコンセントがあるとスムーズです。
電子レンジは電子波と熱を発するため、近くに延長コードを使うのはNG。
専用で1口用意し、周辺には熱に強い素材の壁や棚を設けると安心です。
⬇︎⬇︎お問い合わせや資料請求はこちらから⬇︎⬇︎
コンセント位置を決めるときの5つのチェックリスト
コンセントの位置で後悔しないためには、設置前に確認しておくべきポイントを明確にしておくことが大切です。
「なんとなく」「あとで考えればいいや」で決めてしまうと、生活が始まってから必ず困ります。
ここでは、設計・リフォーム時に必ず押さえておきたい5つのチェック項目をご紹介します。
チェックリストとして活用しながら、理想の配置をシミュレーションしてみてください。

配置前に確認すべきチェックポイント一覧
以下の5つの視点を意識するだけで、コンセントの後悔はぐっと減らせます👇
1. 家電の設置予定場所と使用頻度を確認する
「テレビはここ」「電子レンジはここ」と、家電ごとの配置をイメージしておくと、必要な場所・数・口数が自然に見えてきます。
家電を使う高さや奥行きも考慮しましょう。
2. 家具との位置関係をシミュレーションする
コンセントがタンスやベッドに隠れて使えない…という失敗は非常に多いです。
間取り図に家具のサイズも書き込んで、かぶらない配置を確認しましょう。
3. 掃除や充電など「動線上の使いやすさ」を意識する
コードレス掃除機の充電や、スマホの充電スポットなど、日常的に移動しながら使う機器にも目を向けましょう。
掃除機のコードが届かないと、かなりのストレスになります。
4. 延長コードを前提にしない
「足りなければ延長コードで」と考えるのは危険です。
見た目が悪くなるだけでなく、タコ足配線による火災リスクも高まります。
5. 将来の使い方やライフスタイルの変化も考慮する
「今は使わないけど、将来子供部屋になるかも」「在宅ワークが増えるかも」といったライフスタイルの変化にも備えて、
余裕を持った配置にしておくのが安心です。
以上がチェックリストの紹介でした。
実際に間取り図を手元に置いて、ひとつずつ照らし合わせながら考えると、具体的にイメージしやすくなりますよ。
⬇︎⬇︎お問い合わせや資料請求はこちらから⬇︎⬇︎
まとめ|暮らしやすさは“位置”で決まる

コンセントの位置は、住まいの快適さを左右する非常に重要な要素です。
「とりあえず壁の隅に…」と軽く考えてしまうと、いざ生活を始めてから「あれ?ここにあればよかったのに」と後悔するケースがあとを絶ちません。
本記事では、コンセントの正しい考え方から、部屋別・家電別の最適な配置、さらに増設やチェックリストまで幅広く解説してきました。
どのポイントにも共通しているのは、「生活の動き方に合わせて考える」ということ。
つまり、今の自分の暮らし方にぴったり合う配置を選ぶことで、コンセントは“使える”ものから“暮らしを支える味方”に変わるのです。
そして、将来のライフスタイルの変化も見越して設計することが、長く後悔しないための最大のコツ。
もし今、少しでも「この場所の使い勝手に不満がある」「もっと快適にしたい」と感じているなら、
今こそ一度、あなたの家の“コンセントの位置”を見直してみるチャンスかもしれません。
暮らしの質は、細かなところから生まれます。
そしてその第一歩が、あなたの足元にある「コンセント」なのです。
監修者情報
佐藤 隆(一級建築士・一級建築施工管理技師・宅地建物取引士・千葉市耐震診断士・既存住宅状況調査技術者(インスペクション))